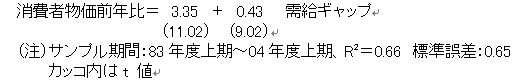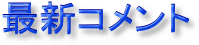
ゼロ金利はいつになったら終わるのか(H17.6.27)
─ 量的緩和政策を問い直す ─
【99年に導入した当初のゼロ金利政策は景気が回復したためデフレ進行下で解除された】
99年2月、日本銀行は金融政策の操作目標であるコールレートをゼロに保つ「ゼロ金利政策」を導入した。橋本内閣の97年度「超デフレ予算」(9兆円の国民負担増加と4兆円の公共投資削減)によって景気回復が崩れ、88年(−1.0%成長)、89年(−0.1%成長)と2年連続のマイナス成長に陥った最中のことである。
その後99年10〜12月期から01年1〜3月期まで6四半期連続でプラス成長が続いたので(00年度は+2.5%成長)、00年8月にゼロ金利政策は解除され、コールレートの操作目標はゼロ%から0.25%へ引上げられた。しかしこの時景気は立直っていたが、消費者物価(生鮮食品を除く、以下同じ)の前年比はマイナスを続けていた。日本銀行はそのデフレを考慮しなかったように見える。
01年度に入ると再び4四半期連続のマイナス成長となり(01年度は−1.1%成長)、消費者物価の前年比下落幅はマイナス1%程度に迄拡大してきた。日本銀行は同年2月に公定歩合を0.5%から0.25%へ、コールレートの操作目標を0.25%から0.15%へ引下げた。それでも間に合わず、01年3月19日に「量的緩和政策」に踏切ったのである。
【日銀当座預金の過剰供給政策(量的緩和政策)はデフレ対策を主眼に導入された】
01年1〜3月期(年率+1.0%成長)には6四半期連続のプラス成長がまだ続いていたが、日本銀行は消費者物価のデフレ傾向が深刻化してきたことと、先行きの景気悪化による一段のデフレ深刻化を懸念して金融政策を転換したのである。この政策転換の主な狙いは、当初のゼロ金利政策(狙いは景気対策)とは異なり、デフレ対策である。
ここで二つの新機軸を打出した。
第一は金融政策の「操作目標」を従来のコールレートから日銀当座預金残高に変え、目標残高を所要準備預金4兆円を上回る5兆円としたことである。1兆円の余剰資金が在るので、コールレートは当然ゼロ金利に張り付いたままになる。しかしその金利はゼロから下へは下がらないので、一層の金融緩和を量的緩和で進めることにしたのである。
その後日本銀行は、長期国債の買オペを増やすなどの手段によって、この目標残高を04年1月までの間に9回引上げて一段の量的緩和を促進し、現在は「30〜35兆円」の巨額に達している。
本年5月に至り、日本銀行は当座預金残高がこの下限30兆円を一時的に割り込むことを容認した。初めて政策修正に動いたのである。(詳しくはこのHPの<最新コメント>“日銀の「札割れ」放置の決定は中途半端”H17.5.20 <論文・講演>“下限割れ容認の次の手は”H17.6.16 参照)
【短期金利ゼロの時間軸を示し長期金利を安定的に低位誘導】
新機軸の第二は、この量的緩和政策を「消費者物価の前年比上昇率が安定的にゼロ%以上となるまで継続する」と市場に約束したことである。この結果、コールレートのゼロ金利が続く「時間軸」が、消費者物価という客観的指標との関連で示されたことになり、将来のゼロ金利の予想期間を安定させることになった。
言うまでもなく、将来の予想短期金利の加重平均にリスク・プレミアムを加えたものが現在の長期金利であるから、これによってゼロ金利政策解除の誤った思惑によって長期金利が上昇することを防ぎ(安定効果)、またリスク・プレミアムを小さくして長期金利を引下げることに成功した(下落効果)。
【二つの新機軸の副作用】
以上の二つの新機軸は、かなり変則的かつ大胆な手法である。過剰な日銀当座預金の存在によって、コール市場の機能は麻痺し、また銀行は預金吸収の意欲を無くして、銀行経営は異常な状態に追い込まれている。また金融政策の運営を消費者物価だけにコミットすることは、将来、万一物価安定下の景気過熱や資産バブルが発生した時(例えば1988年)には極めて危険である。引締め政策への転換が遅れて景気過熱とバブルの膨張が行き過ぎ、その後の反動不況を「失われた10年」のように長く深くするからである。
しかし日本銀行は、それらを全部承知の上で、敢えてデフレ克服最優先の政策に踏み切ったのであろう。1988年とは異なり、当面の日本経済では景気過熱やバブル発生の懸念が出る程に経済が立直れば、むしろ大歓迎であり、その時消費者物価の前年比はゼロ%以上になり、安心してゼロ金利政策から脱出できると考えているのであろう。それ迄は、コール市場の機能麻痺や銀行の預金吸収意欲喪失には目をつぶろうとしているのであろう。
【量的緩和政策のメリットとデメリット】
では、この大胆な新機軸は、デフレを克服し、経済を立直らせる効果を少しは発揮したのであろうか。
前述のように長期金利を低位に安定させる効果は確かにあった。そのことによって、企業投資や住宅投資を下支える上で、なにがしかの効果があったかも知れない。また財政の金利負担を減らす効果も大きかった。
更に、日銀当座預金に過剰資金を積むことにより、万一の金融システム不安に事前に備える効果があった。もっとも現在では、金融不安の時期は過ぎたので、その役割は終わった。
効果は以上の二つだけである。問題はそれによってデフレの克服や景気立直りの効果が果してあったかどうかである。実際には、目標残高の引上げでいくらベースマネーを増やしても、肝心のマネーサプライは増えなかったし、消費者物価は現在も下落を続けている。デフレ克服には役立たなかったのではないか。景気も輸出主導型で、国内需要は停滞したままである。
金融政策運営上の問題も生じている。日銀当座預金の目標残高を、当初の5兆円から現在の30〜35兆円に引上げる過程で、日本銀行は緩和を促進する効果があると説明してきた。しかし実際には、何の効果も促進されていない。長期金利が一段と低下したわけでもない。01年の量的緩和政策導入時と同じ1.3%前後だ。金融システム安定の効果も、既に使命を終っている。
それなのに「緩和促進」と説明して目標残高を引上げたことにより、今度は目標残高を引下げて余剰資金を圧縮すべき時になって、「引締め」転換と勘違いされる状況を作ってしまった。
それを恐れて日本銀行は、現在目標残高の引下げに極めて慎重である。将に自縄自縛ではないか。
【予備的動機減退に見合った目標残高の引下げに踏み切れ】
日本銀行は、いまどうやって量的緩和政策とゼロ金利政策の幕引きをするか迷っているのではないか。取敢えずは、「金融システムの安定に伴う予備的動機の通貨需要減退に見合って日銀当座預金の圧縮を図る」という理由で目標残高を少しずつ引下げるのがよいと思う。これが「引締め」転換と勘違いされない最善の策であろう。
しかしこれは、「出口」への助走にすぎない。本当の「出口政策」は、目標残高を所要準備残高の4兆円近く迄引下げ、操作目標を日銀当座預金からコールレートに再び戻し、コールレートをゼロ金利より上に徐々に誘導することである。しかし、「消費者物価の前年比が安定的にゼロ%以上」になる迄は量的緩和政策を続けると市場に約束した以上、これを守らずに「出口政策」を実施すれば日銀に対する信頼感が失われる。一度失われれば、今後は「市場の期待」に働きかける日銀の発言は、全部信用されず無効になってしまう。そんなに大きな犠牲を払う訳にはいかないから、日銀としては消費者物価の前年比がゼロ%以上になる迄は、デメリットには目をつぶって本格的な「出口政策」を控えざるを得ない。
そこで問題は、何時消費者物価の前年比が安定的にゼロ%以上になるかである。
下の第1図に示したように、中国における基礎資材のボトルネック・インフレや世界的な原油価格高騰に伴って、昨年4〜6月期から国内の企業物価指数の前年比は7年振りにプラスとなり、一時は+1%を超えた。しかし、消費者物価は昨年9月に前年比が一時ゼロ%になったものの、その後は第1図で確認できるように再びマイナスを続けている。
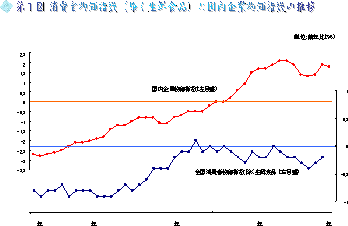
クリックで拡大
【個別価格の動きから見ると本年10月以降にデフレ解消の可能性】
企業の段階で物価が上昇しているのに、何故消費者物価は上昇しないのであろうか。
下に示した第2図は、消費者物価を構成する諸価格を、財(除く農水畜産物)、農水畜産物(除く生鮮食品)、一般サービス、および公共料金の4グループに分けたものである。
昨年9月以前の消費者物価前年比のマイナス幅に一番大きく寄与していたのは、財(同)の価格の下落であったことが見て取れる。しかしその後現在までは、企業物価の上昇を反映して、消費者物価の中の財(同)の価格も上昇している。
代って消費者物価の足を引張り、前年比をマイナスにしているのは、公共料金と農水畜産物(同)の下落であることが、グラフから読み取れる。公共料金では、昨年11月と本年1月の通信料金引下げが、消費者物価全体の前年比を0.1%ずつ引下げる効果があった。農水畜産物(同)では、昨年10月の米価値下がりが、消費者物価全体の前年比を0.2%引下げる効果を持った。
この二つの効果を合わせた合計0.4%が現在の前年比マイナスに大きく寄与している。これが前年比マイナス幅の中から消えるのは、本年10月から明年1月の間である。現在の消費者物価の前年比マイナス幅が−0.2%(本年5月)であることを考えると、この10〜1月の間の前年比−0.4%の引下げ効果消滅は、消費者物価の前年比をプラスに転じる可能性を十分持っていることになる。
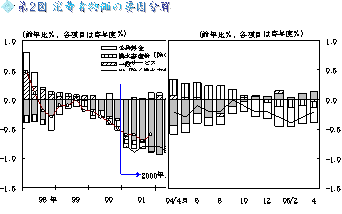
クリックで拡大
【物価を大きく左右するのはマクロの需給状況】
しかしこの予想は、他の条件が一定の場合の話であり、今後の需給状況を反映して新たに上昇する項目、新たに下落する項目の動きによっては、話が変わってくる。
そのような個別価格の動きを全体として見たものが物価指数であるが、それを大きく左右しているのは、日本経済全体のマクロの需給状況である。個別価格の事情で、マクロの需給状況の逼迫がないのに物価が上昇すれば、実質購買力が減少して需要は減るので、マクロの需給が緩和し、やがて物価は反落する。その逆もまた真である。
そこで、日本銀行が推計したGDPベースの需給ギャップと消費者物価の前年比をグラフに描いて対比してみたのが、下の第3図である。両者はかなり似た動きを示しており、消費者物価の前年比が国内のマクロの需給状況によって大きく左右されていることが分かる。
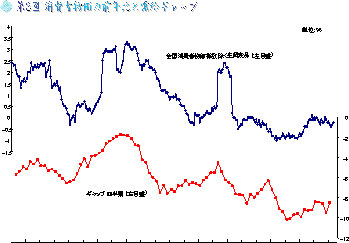
クリックで拡大
【本年度に1.5%以上成長すれば需給面からデフレが解消する可能性】
どの程度左右されているかを見るために、日本銀行がこの需給ギャップで消費者物価の前年比を回帰した結果を見ると、次の通りである。
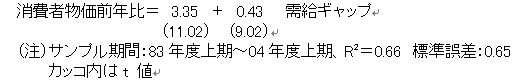
この回帰式から、消費者物価の前年比がゼロ%になる需給ギャップを計算すると、
−3.35÷0.43=−7.79
となる。つまり、需給ギャップが−7.8%あたりより更に縮めば、消費者物価のデフレ(前年比マイナス)は解消することになる。因みに、本年1〜3月期の需給ギャップは−8.5%であるから、あと0.7%縮めばよいことになる。
しかし、この回帰式の標準誤差や決定係数の大きさから考えると、前年比で0.5%程度の誤差は見ておかなければならないと考えられる。
従って、05年度に1.5%前後のプラス成長をすれば、マクロ的な需給ギャップに関する限り、消費者物価のデフレ解消の条件が整う可能性がある、という程度のことしか言えないであろう。
【年末から来年前半にかけてのゼロ金利解消の可能性は四分六分】
以上の個別価格や需給ギャップの分析から言えることは、本年度の日本経済が03年度(+2.0%成長)や04年度(+1.9%成長)並みの成長をすれば、本年度下期には消費者物価の前年比がプラスに転じ、量的緩和・ゼロ金利からの出口政策が日程に上ってくる可能性が高い、と言うことであろう。
しかし、01年度(−1.1%成長)や02年度(+0.8%成長)並みの成長では、例え米価や通信料金の値下がりの影響が無くなっても、消費者物価のデフレは続き、量的緩和・ゼロ金利政策の解消は出来ないであろう。その場合日本銀行は、前述した量的緩和・ゼロ金利政策の様々な問題点に悩み続けることになろう。
どちらに転ぶかのボーダーラインは、前述の通り+1.5%前後の成長よりかなり高いかかなり低いかであり(誤差考慮の要)、またデフレが解消するとしても時期は早くて本年10〜11月以降であろう。
なお、仮に原油価格の一層の高騰によって消費者物価の前年比がゼロ%以上になったとしても、1.5%以上の成長でマクロの需給バランスが好転していない場合は、ゼロ%以上の物価上昇は長続きせず、前年比はマイナスに戻るであろう。このようなコスト・プッシュ型の消費者物価上昇は消費の実質購買力を減少させ、需給バランスの悪化から石油関係以外の消費者物価が下落するからである。
本年度に+1.5%以上の成長が出来るかどうかは、米国と中国などの景気に左右される輸出の動向と、国内の雇用・賃金を背景とする消費の動向などに懸っている。現時点では、下期再上昇で+1.5%を超えるか、停滞持続で+1.5%に届かないか、二つのシナリオがあり得るが、私の判断は四分六分で後者の可能性が高いと見ている。中国の成長減速や原油高止まりに伴う非産油途上国の経済停滞、米国の成長減速などによる輸出の鈍化が大きく、また国内の雇用・賃金の回復が鈍いからである。従って、本年10〜11月以降来年前半までのゼロ金利解消の可能性も、予断を許さない。来年いっぱい、ずるずるとゼロ金利時代が続く可能性もかなりある。その場合は、量的緩和政策のデメリットがますます問題となり、日本銀行は難しい立場に立たされるであろう。
同時に、金融政策にばかりシワを寄せ、持続的成長を実現できないでいる財政政策や経済改革の責任も、改めて問われるべきであろう。
![]()